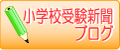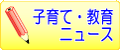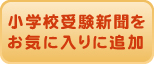立命館小学校 深谷 圭助 校長先生(当時)インタビュー
立命館小学校の特徴を教えてください。2006年の4月に開校して以来、「ここで学んだ子ども達が世界を変えていく」というキャッチフレーズを掲げ、国際社会のリーダーになる子ども達を育てていくためには、小学校としてどうすれば良いのか、或いは一貫教育としてどうすればいいのか教育の4つの柱をもとに実践してきました。 その中で特に注目されてきているのは、1つめの「確かな学力を形成する教育」です。 21世紀に入って以来、学力の問題が特に社会的意識として高まってきた時期に、立命館小学校が開校したわけですから、学力に対してどのように考えるべきか、小学校としてどのような学力を育てていくべきなのかを真摯に捉えてきました。 特色的な教育としては、1年生から6年生まで「モジュールタイム」を設定しています。大脳生理学に基づいた前頭前野を活性化する音読や名文の暗唱、簡単な計算を反復して行っています。計算力を付けること、名文を暗唱することも重要ですが、脳を活性化することにより朝からフル回転で頭を使うための準備運動として捉えています。 私たちの学校では専科制を導入しています。どのクラスも同じ質の教育を提供出来ます。教材についてはカリキュラムを進めていくためには 専科制の導入による系統的な学習が各学年において必要です。また、学年があがるにつれて展開されていく専科を大切にするためにも専科担任制を採用しています。 1年生から4年生までをファーストステージと呼んでいます。 ファーストステージでは3つの科目を用意しています。1つは「読書の時間」、1つは「そろばんの時間」、1つは「ロボットの時間」です。 セカンドステージの特色ある科目では、国語を「リテラシー」と「古典」、「文学」に分けて学習しています。 算数に於いても、代数と幾何、数的な領域と図形的な領域に分けて指導しています。その授業に於いて何を目標にするのか、何を目指すのかを明確にして授業を設定するカリキュラムを作っています。 2つめの柱の「真の国際人を作る教育」では、1年生から英語の教育を週2〜3時間設定しています。英語はモジュールタイムにおいても学んでいます。ネイティブに近い発音が出来るように、ネイティブ教員と日本人教員のティームティーチングを行い、きめ細やかな教育をしています。 高学年になると、英語検定にも積極的に挑戦しています。6年生終了時までに全員3級合格を目標にしています。 3つ目の柱「豊かな感性を育む教育」では、特に「図工・造形教育」、「音楽教育」、「図書館教育」の3つの観点から感性の教育に取り組んでいます。 「音楽教育」に関しては、とくに2009年度は、1年生から6年生まで揃う完成年度を祝して、ベートーベンの交響曲第9番を1年生から6年生全員、保護者・教員がドイツ語で歌おうと、4月から練習を積み重ねて来ています。 最後の「高い倫理観と自立心を養うこと」に関しては、道徳教育の新しい取り組みとして、「立命科」を設けています。そして、「ハウス制度」による、異年齢集団ならではの協力・協調を通して子ども達の心の教育を行っています。「立命科」に関しては、論語の素読、そしてその中身を学ぶという学習の場面もありますし、立命館に関わりのある人々の生き方について学ぶ事もあります。 「ライフスキルズ」といって、子どもたちが生きて行く上で出会っていく葛藤やいろいろな人の考えを聞いていく学習場面があります。例えば、車座になって順番に出来事や事柄について自分の考えを発表していくという学習場面があります。そういった様々な形での道徳教育を試みています。 ハウス制度に関しては、どうしても学校教育と言うのは同じ年齢のお子さんが集まっている集団ですので、限られた人の中での関わり合いになりますが、1年生から6年生までの違った年齢の縦割りの集団を作って共に活動していきます。年上の子達は下の子の面倒を見たり、年下の子は年上の子の話しを聞いたりしながら、関わりを持っていきます。具体的には、清掃はハウスの小グループであるファミリーで分担して行います。清掃指導も上の学年が下の学年を指導していまして、上級生が下級生に社会生活上のルールを教える時間でもあります。行事においては、互いに協力し合いながら、1つの目標に向かっていきます。 以上が、4つの教育方針です。 2009年度は面倒見の良い学校づくりを目指しています。子ども達に対する学習面でのサポート、生活面でのサポートを丁寧に行っています。 具体的には、新型インフルエンザが流行して本校も1週間休校したのですが、全員の子どもたちに宿題・課題を郵送し、1人1人の子ども達に毎日電話をし、声を聞き、子ども達を励ますといったことをしてきました。本校は私学で、地域の学校ではないため、距離的に遠い所から通って来ているお子さんも多いのですが、そういったハンディを乗り越えた丁寧な指導、きめの細かい指導を目指しています。 次に一貫教育の話をします。 小学5年生〜中学2年生をセカンドステージと呼んでいますが、そのセカンドステージでは小学校の教員と中学校の教員のティームがあり、来年の4月には初めて中学校に進学していく子どもたちの準備を進めています。 立命館は大学・大学院まで備えている総合学園ですが、小学校の時点で立命館の中だけで子どもの夢や目標を達成出来るとは思っていませんので、立命館に縛るということではありません。子どもたちの将来羽ばたいて行きたい進路や目標を大切にして、12年間の一貫教育をしていくことが私たち目標です。
立命館小学校の児童さんたちはどのようなお子さんでしょうか?とても素直な子どもたちが多いです。どんどん吸収しようという意欲にあふれています。家庭で非常に大切に育てられているなと思います。みんなとても前向きです。周りからも期待されていますし、それに応えたいと思っている子が多いと思います。それは、とても重要な事と思います。世間では、それをプレッシャーと言うのかも知れませんが、適度なプレッシャーというものは必要だと思います。人間は期待されるからこそ、頑張れるわけで、頑張ることを美徳とするような社会にしていかなければならないと考えています。男女の比率は半分半分です。教育的判断により意図的にそのようにしています。
遠方のお子さんは不利でしょうか。入試に関して全く問題ありません。ただ、新幹線通学は認めていません。合格後に引っ越して来られるのは認めています。通学範囲としては、滋賀県では能登川あたり、兵庫県では西宮、芦屋あたりから通学している子どももいます。遠方の子どもほど早く登校し、近所の子ほどゆっくり登校して来ますね。そして、遠方の子どもほど、休みませんね。生活のリズムがきちんと出来ているのだと思います。
立命館小学校の児童たちはどのように育ってもらいたいと思いますか。「自分に自信を持って羽ばたいてほしいです。先の学長である末川先生の言葉である「理想は高く、姿勢は低く」という言葉がありますが、そんな人になってもらいたいです。 「生きる構え」、「前を向いて生きていく構え」を自覚して生きてもらいたいと思います。勉強にも運動にも積極的に取り組んでほしいです。勉強することは1つの方便に過ぎません。「生きる構え」を小学校時代にこそ学んでほしいのです。 「生きる構え」、「前を向いて生きていく構え」を身につけるには、まず、物事に取り組むときに意欲を持って取り組むことだと思いますね。モジュールタイムでもそうです。さあ、今日も1日頑張るぞといった構えで、取り組むことが大切でしょう。物事をするに、決して受け身ではなく、自分なりに気持ちを高めて取り組んで行くことが大切だと思います。
これから小学校受験をされるご家庭に伝えたいことはどのようなことですか。本校は、教育に関してきちんと責任を取ります。そういった意味では、期待していただいて良いと思います。
取材協力 幼児教室 けいkids+
|