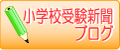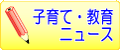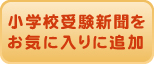洗足学園小学校 稲田 拓 校長先生 インタビュー
洗足学園大学附属幼稚園の園長先生をお勤めになられていた稲田先生が、この度洗足学園小学校の校長先生を兼任されることになりました。
園バスを送る時に手を振るのが毎日の日課だった稲田先生ですが、
どのようなお人柄で、どのようなお考えをお持ちの校長先生なのかインタビューしてまいりました。
稲田 拓 校長先生 プロフィール |
1933年生まれ。
慶応義塾大学文学研究科修士課程修了。
慶應義塾大学教授、1980年慶應義塾高等学校校長就任、1990年慶應義塾湘南藤沢中・高等部初代部長就任。1999年より洗足学園大学附属幼稚園長に就任。
2004年まで短期大学幼児教育科長を兼務。
2007年12月洗足学園小学校校長に就任。
慶應義塾大学名誉教授。
洗足学園音楽大学名誉教授。
|
校長先生インタビュー
|
稲田校長先生は附属幼稚園の園長をお勤めになっていました。そして洗足学園の理事でもあります。稲田校長先生から見て、洗足学園小学校はどのような学校ですか?
洗足学園小学校は、低学年の基礎力を大事にする学校です。そして、色々な面で充実した小学校です。
学力以外の、人間としてとても大事なことが学べる小学校だと思っています。
情操面でもしっかりとした教育を行っており、知識偏重な座学中心ではなく、社会経験もたくさん経験できる学校ですし、今後もさらに強化していきたいと考えております。
最近では、中学受験だけが目立ってしまっていますが、中学受験実績はあくまでも結果なのです。
通常のカリキュラム、教員達の工夫や努力がたまたま中学校受験の結果に表れているだけのことなんです。
基礎力学習が実を結んでいると言えるかもしれません。
現在、附属幼稚園から約30名が進学してきます。幼稚園園長と兼任といっても、附属幼稚園からの進学者の上限人数約30人というのは変わりません。色々な事情があって変わる時は何年も前から予告します。
|
稲田先生が大事にしていることはどんなことですか?
私が大事にしているのは、対話やコミュニケーションです。
児童と教員、保護者と教員、教員と学校長、全てにおいて対話とコミュニケーションが重要です。
対話が人間関係を構築していきます。
児童と教員が心を通わすということは、児童の後ろにいる保護者と学校が心を通わせるということなんです。
それが私学の原点だと思います。それが今までは足りなかったかもしれませんね。
園長先生と小学校校長を兼任するなんて大変ではないですか、と心配される方も中にはいらっしゃるようですが、児童と教員が人間関係を築くとうまくいくように、教員と学校長の人間関係が構築できれば必ずうまくいきます。幸い、小学校の教員も幼稚園の教員も本当によく働いてくれています。そういう意味で私は恵まれているのだと思います。現場の教員達との信頼関係がとても大事なんです。
「それはあなたに任せておいたでしょう」とは絶対に言わないというのが、長年校長職に就いている私の原則なんです。報告をしっかりすることと、一生懸命やることが大前提ですが、そういうことを絶対に言ってはいけないと思っています。
教員には、親御さんの気持ちを汲んであげられるような教員になって欲しいと言っています。
教育面で大事にしていることは、体験学習による実体験はとても大事にしたいですね。
体験学習から、「ものを考える力」を養うことができるからです。
経験の中から生み出す知識というのは長い人生において大変重要なのです。
それと、「ものを考える」という姿勢を大事にしたいですね。こういう姿勢が身についている子どもは、将来、どんなことでも困難を乗り越えていくことができます。
全てにおいて、物事を自分なりに考えることができない幼児が増えているような気がします。
考える習慣が身についていないと、日常的な学校生活の中でも、「ひらめき」が生まれません。
「ひらめき」は学力面でも、人生においても私は重要と考えています。
どんなご家庭のお子さんに入学して欲しいですか?
社会に貢献できる子どもになって欲しいと思うご家庭のお子さんに入学していただきたいです。
自分のことは自分でやるということ、他人に迷惑かけないというのは基本中の基本です。その上で他人を手伝ってあげる、他人に尽くしてあげられるというのをプラスして欲しいのです。
この学校の始まりは戦後の裁縫塾です。女性が手に職をつけて自立し、世の中のためになって欲しいというのが始まりなのです。そういう学校を作るのが当時では社会奉仕の一つの方法だったのです。
それが創立者前田若尾先生の精神だったので、その考えは大事にしたいですね。
受験に合格すればなんでもいい、なんて思っている親だということが面接で分かったら、申し訳ないがそういうご家庭はお断りしたいと思います。勉強がよくできるよりももっと大事なことがありますから。
ご家庭に望むことは?
1つめは、一人の人間としてきちんとすることです。特に下の年齢ほど。
簡単に言えば、日常生活をちゃんと行うことです。でもこれはとても難しいことだと思います。ご両親の心構えと努力と社会常識がないとしっかりとした日常生活を行うことは困難です。ましてや、子どもにさせることなんてできません。
基本的なことを大事にして欲しいと思います。
2つめは、「過程」を大事にしてください。
お子さんには3ヶ月前のお子さんと比べて褒めてあげて下さい。一歩ずつ前進させていく方向性が重要です。
一生懸命やることは大事なのですが、それが完成ではないのです。あくまでも成長の過程です。明日やったらもっとうまいぞ、というのが向上の印だと思います。
お子さんに完璧を求めないで下さい。昨日より今日が成長していればそれで良いのです。発表会などで演奏が上手くに出来なくたって良いじゃないですか。その発表会で行う演奏ががそれまでの成長の表れなんです。
チャレンジすることは大事です。でも結果よりも過程が重要だということを伝えたいのです。これは学力面でも同じことが言えます。公式に当てはめて答えを出すのも良いですが、その公式の意味をよく考える、そういった過程が将来大事になっていきます。
過程とは少し話しが逸れますが、子どもを注意する時、子どもの気持ちを理解しているのか、していないのかでは大きく違うと思います。
幼児ですからいたずらもするでしょう。そういった時に、その年齢の子供たちのいたずらしたい気持ちを理解した上で、その時注意が必要であればしてもらいたい。子どもの気持ちを理解せずに自分の価値観だけで叱り付けるのは止めて欲しいと思います。いたずらしたいという気持ちも一つの成長過程なのです。
3つめは、 方向性をしっかり持って子育てして欲しいですね。ご両親が子育てに関してしっかりとした方向性を持っているご家庭は強いですね。子育てには様々な予想外の出来事が起きます。その時に、方向性さえ見失わなければどんなことでも対応できますし、また、そのお子さんにとっても良い判断ができます。遠回りしたとしても、たとえ道から逸れようとしても、方向性さえしっかり持っていれば道に迷うことはありません。
4つめは、幼児期に遊ばせないで、知識や知力を身につけさせることばかりをやっていると、長い目で見たとき損ですと言いたいです。それは私の体験から自信を持って言えることです。
どのような小学校にしたいですか?どのような子どもに育てたいですか?
将来、社会に出て社会に貢献できる子どもを育てられる小学校にしたいと思います。
児童は皆、教養ある社会人になって欲しいと思います。その土台を洗足学園小学校で身につけさせたいと考えております。
洗足学園小学校は塾や教室ではありません。
確かに学力向上の研究はしていますよ。でもそれだけを行うのは塾なんですよ。学校というのはそれだけじゃなくて、情操面や生活とかマナーとかを含めて教える場ですからそれらもきちんと教えます。
それには心の通いあった学校でなければならないと思います。
それと、周りの状況を見て物事を判断できる子どもになってもらえるように育てていきたいですね。
それには、みんなで色々なことを考える機会を作っていきたいと思います。状況によった判断力を身につけさせてあげたい。
気力、体力、判断力を身につけさせる方向でもっていきたいと考えています。
そして、
嫌なことをされたら、周りが気付いてくれるまで待っているのではなく、自ら「やめてくれ」といえるような、自分の意思をしっかり発言して
独立した人間として行動できるような強さをもった人間になって欲しいと思います。社会に出てから凄く大事なことなんです。そういった生徒に育って欲しいと思います。
第一志望で入ってきても、第二志望で入ってきても、洗足学園小学校に入ってよかったなと思わせる学校にしたいです。
保護者の方たちにメッセージをお願いします。
保護者の方は前向き志向、未来志向であって欲しいと思います。
当校を受験していただけるのであればそれはとても光栄なことです。
でも、残念な結果だとしても落ち込む必要はどこにもありません。
落ちたっていいじゃないですか。本命の小学校に落ちたからってがっかりすることはないんです。合格をもらえた学校で頑張ればいいんです。もし、その学校に足りないところがあると感じるのであればご家庭で補えば良いんです。
入学した学校がその子にとって最高の小学校なのです。
子どもは敏感ですから、保護者の落ち込んだ態度や学校に対する不満をすぐに感じ取ってしまいます。
子どもがこの学校は良い学校じゃないんだ、と先入観を持ってしまうとその子は絶対に伸びません。
後ろ向きの考え方は子どもにも影響するので絶対に良くありません。
保護者の方もお子さんも、良さそうなことはどんどんチャレンジしてください。チャレンジしてみてダメだったらそれでいいじゃないですか。何にも落ち込む必要はないんです。次に他の方法や事柄を見つければいいんです。
どうか保護者の方は前向きに考えるようにしてください。そうすればお子さんにも必ず良い影響がでます。
 トップへ トップへ
|